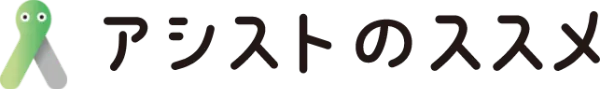学びプラス情報
【心理学】心理学で読み解く、ご褒美バレンタイン
-
心理
記事のカテゴリー
-
その他(コラム)
こんな方に読んでほしい
-
モチベーションを上げたい方
-
心理学・コミュニケーションに興味のある方
記事から得られること
-
最近のバレンタインイベントの多様化と心理学的考察
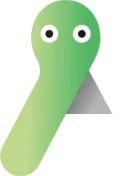
もうすぐバレンタインデーがやってきます。
チョコレートの原料となるカカオ豆の不作や円安の影響で、バレンタインを前にしてチョコレートの価格が高騰しています。
そんな中、数年前から「自分へのご褒美チョコ」需要は増加傾向に、
逆に「好きな相手へのチョコ」「職場へのチョコ」需要は減少傾向にあるようです。
バレンタインにおけるチョコ文化も時代とともに変化しているようですね。
今回は自分へのご褒美チョコに焦点を当てて、心理学で考察してみます。
・自分へのご褒美はモチベーションアップに効果的
私たちは何かを達成すると嬉しくなったり達成感を感じたりします。
そして「また頑張ろう!」と思うようになります。
このとき脳内ではドーパミン(快感ホルモン)が分泌されていて、それが私たちにやる気やモチベーションを感じさせます。
こうした脳のシステムを『報酬系』といいます。
この報酬系を利用することで、様々なモチベーションの向上や維持をすることができます。
「これを頑張ったら、後でご褒美が待っている」というふうに、自分が魅力を感じるご褒美を後に設定しておけば、「またあの快感を味わいたい」と脳の報酬系が働き、様々なことに対するモチベーションを維持向上することができます。
・自発的に動くモチベーション
アメリカの心理学者であり経営学者のダグラス・マクレガー氏は、『XY理論』という、人間の動機付けに関わる理論を提唱しました。
X理論とは「人間は本来怠惰であり、仕事をさせるには命令・強制が必要である」という考え方です。
一方、Y理論は「人間は自分が設定した目標に対し積極的に行動する」という考え方です。
どちらも私たちの心を別の角度から捉えているといえますが、自発的に動くモチベーションを維持するためには、Y理論に注力する方が効果的といえます。
そのためのツールとして、自分へのご褒美によって報酬系を活用することは有効です。
・ご褒美が逆効果になる場合
目標達成とご褒美までの課程が長すぎたり、目標そのものの設定が高すぎたりすると、途中で挫折してしまったり、途中で諦めてしまったりしてしまう場合があります。
なので自分にとって適切な達成目標と、途中の達成目標を設定することが必要です。
・自己理解が大切
自分が何に対してやりがいを感じるのか、また何に対して不快感を感じるのか、
こうした自己理解ができていれば、目標やご褒美の設定は自分に合ったものができるようになります。
しかし自己理解が足りないと、何が自分にとってご褒美になるのか分からなかったり、
自分にとって適切ではない高さの達成目標を設定してしまいがちです。
自分へのご褒美チョコを用意したとしても、そもそもチョコレートが嫌いだったらモチベーションは上がりませんよね。
自己理解を高めるためには、色々な体験に対して予断から決めつけてしまわずに、まずは経験してみることが大切です。
また、これまでの経験を振り返ってみることも役立ちます。

自分へのご褒美は、モチベーションアップにつながります。
今年のバレンタインは、チョコレートに拘らず、ちょっといいものをご自身にプレゼントしてみるのはいかがでしょうか?
自己肯定感も少し上がるかもしれません。
参考
ウィキペディア:報酬系
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%B1%E9%85%AC%E7%B3%BB
ウィキペディア:XY理論
https://ja.wikipedia.org/wiki/XY%E7%90%86%E8%AB%96
関 一真
-
心理
担当
京都四条烏丸校
所属
NLP™トレーナー、心理カウンセラー2015年より京都校、大阪梅田校にて心理学系講座を担当。優秀講師賞受賞。個人で心理カウンセラー、占い師としてクライエント様に相談援助を行う。日本語教師(日本語教育能力検定試験合格)、社会福祉士資格保有
この講師の記事を見る