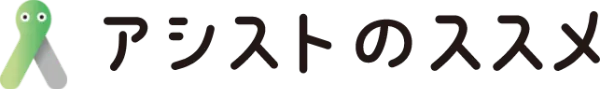学びプラス情報
【日本語】日本語を教えるために理解すべきこととは
-
日本語教師
記事のカテゴリー
-
学習に役立つ豆知識・スキル
こんな方に読んでほしい
-
日本語教師養成講座受講生
記事から得られること
-
日本語と日本人の文化、メンタリティのつながりに関心を持っていただく
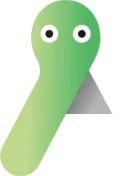
私たちが普段何気なく話している日本語、そして日本語によるコミュニケーションには、
日本の文化や日本社会で大切にされている人間関係のあり方が、色濃く影響を与えています。
日本語や日本語によるコミュニケーションを外国人、特にアジア圏以外の外国人に教えるには、日本語の対人関係、中でも「上下関係」に敏感である部分も理解しておく必要があります。
◆儒教文化圏の日本語
戦後三四半世紀以上経った現代の日本であっても、いまだにその社会を考える上で重要な基本軸として「上下」は外すことはできません。
この「上下」の基準は、過去の身分制や封建制といった社会制度的な要因によって醸成されてきた基準ですが、それが社会に浸透し人間関係が形成されるうちに、コミュニケーションにおいてもそれを確認したり表現したりすることが重要視されるようになりました。
日本語は「敬語」という対人関係のコミュニケーションを発達させてきました。
・誰が誰の上か
・誰がヨソの人で誰がウチの人か
こうしたことを表すことがそれによって容易になりました。
また、相手を呼ぶときに使う呼称でも
・目上の人を呼ぶときには肩書きや親族名を用いる
例:「先生」「お父さん」「お兄ちゃん」
・目下の人を呼ぶときには代名詞や名前を用いる
例:「君」「〇〇ちゃん」
×「生徒」「弟ちゃん」
というように、何かを言うという行為には常に上下などの人間関係を確認する意味合いが含まれました。
◆儒教と日本語
日本語の上下を基準とする価値観の由来として、紀元前6~5世紀に孔子が体系化した「儒教」が挙げられます。
儒教は「仁・義・礼・智・信」を徳目とし、それを高めることで「父子・君臣・夫婦・長幼・朋友」といった人間関係を維持することを説く教えです。
日本には5~6世紀ごろに紹介されましたが、江戸幕府がその思想的支柱として儒学(朱子学)を採用し、明治政府も奨励したため、日本での影響力は長く続きました。
中国を中心に儒教の影響が強い地域を「儒教文化圏」と呼びます。
儒教文化圏の多くの言語は尊敬語や謙譲語といった敬語の体系を持ちます。
例えば日本語や韓国・朝鮮語、かつての中国語、モンゴル語、チベット語、タイ語、ジャワ語などです。
これらの言語は東アジア~東南アジアにかけて分布していて、
例えばヨーロッパの言語には敬語体系は見られません。
たたし、儒教文化圏でもベトナム語のように敬語が発達しなかった言語もあります。
現代の中国語には敬語は顕著には残っていませんが、
これは戦後の共産革命によって敬語がほぼ一掃されたためです。
◆上下関係の暗黙のルール
上述の敬語体系は表に現れている分、幾分分かりやすいかもしれません。
しかし日本語には言語の内容面でも上下を反映した現象が見られます。
例えば
・目上の人の願望や感情に言及することは控えるべき
という暗黙のルールがあります。
これだけではピンと来ないかもしれませんが、
例:「先生、コーヒーお飲みになりたいですか?」
「先生、怒っていらっしゃいますか?」これには敬語が使えているにも関わらず、多くの人が違和感を感じるのではないでしょうか?
実際、私たちはこれらに相当する言い回しとして、
例:「先生、コーヒーお飲みになりますか?」と単なる行為を尋ねたり、
例:「先生、こちらになにか不手際がありましたでしょうか?」と話し手側のことを尋ねる形にしたりします。
しかし、これがひとたび親しい友達のような間柄になれば、
例:「ねえ、コーヒー飲みたい?」
「ねえ、怒ってる?」という表現は自然に感じるのではないでしょうか。
日本語では、下から上に向けて願望や感情といった相手の私的な領域に触れることが
不躾で失礼にあたると見なす暗黙のルールが存在します。
ちなみに、韓国・朝鮮語や中国語にはこういったルールは必ずしも存在しません。
日本語を勉強する学習者が自然な日本語を使えるようになるには、こうした文化に沿って発達した表現も理解する必要があります。
特に敬語体系が無い言語が母語の学習者の場合には、こうした敬語体系の理解が、日本でのスムーズなコミュニケーションには必要になります。
参考文献・サイトURL・画像 等
滝浦真人『日本語とコミュニケーション』
一般財団法人放送大学教育振興会2015年
https://amzn.asia/d/1hAzvAZ
関 一真
-
心理
担当
京都四条烏丸校
所属
NLP™トレーナー、心理カウンセラー2015年より京都校、大阪梅田校にて心理学系講座を担当。優秀講師賞受賞。個人で心理カウンセラー、占い師としてクライエント様に相談援助を行う。日本語教師(日本語教育能力検定試験合格)、社会福祉士資格保有
この講師の記事を見る