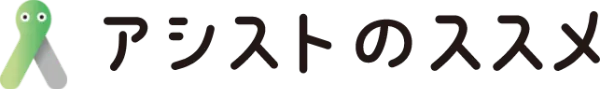学びプラス情報
納涼だけじゃない!なぜ人は夏にホラーを求めるのか?
-
心理
記事のカテゴリー
-
その他(コラム)
こんな方に読んでほしい
-
全受講生・修了生
-
心理学・コミュニケーションに興味のある方
記事から得られること
-
ホラーを潜在的に求める理由
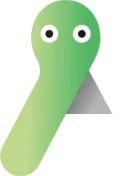
毎日うだるような暑さ、夏真っ盛りです。
体調管理を怠らず、学習を進めてくださいね。
みなさんにとって夏の風物詩といえば何でしょうか?
色々ありますが、「夏といえばホラー」という方も多いのではないでしょうか。
そもそもホラーがなぜ夏の風物詩なのでしょうか?
そして何故人はわざわざホラーを求めるのでしょうか?
今回は日本独特のホラー文化と、恐怖に関する心理学をお届けいたします。
ちょっとクールダウンしていただければ幸いです。
ホラーが夏の風物詩なのは日本だけ
日本では夏になると怪談ライブや心霊番組、ホラー映画の公開と、
ホラーシーズンがやってきます。
しかしこれは日本だけの文化であることをご存じでしょうか?
海外では特にホラーと季節が結びつくことは無いようです。
強いて言えば、アメリカやイギリスなどでハロウィーンの季節にホラー映画の公開があるくらいでしょうか。
日本でホラーと夏が結びついたのは、江戸時代の歌舞伎に影響が大きいようです。
江戸時代の芝居小屋にとって夏は暑さで客入りが悪く、閑散期でした。
そこで何とかお客さんを喜ばせようと、趣向を凝らした仕掛けを取り入れた怪談物を上演しました。するとこれが「涼み芝居」として大当たりしました。
このとき江戸の三大怪談といわれる「牡丹燈籠」「四谷怪談」「番長皿屋敷」も大流行しました。こうして夏の怪談が現代まで風物詩として続いているのです。
恐怖を感じるとどうなる?
恐怖の感情は生物にとって生き残る上で重要な感情です。
恐怖があるからこそ、生物は危機に対して逃げたり立ち向かったりすることができます。
恐怖を感じるとき、私たちの脳内ではアドレナリンというホルモンが放出されます。
アドレナリンには、心臓の働きを活発にし全身の血流を促進する働きや、
集中力を高める働き、気管支を拡張させ呼吸を促す働き、血糖値を上昇する働きがあります。
これらの働きによって、私たちは危機に対して立ち向かうか逃げるか対応することができます。
この反応を「闘争・逃走反応」といいます。
人は何故ホラーを見たがるのか?
恐怖はネガティブで激しい感情であるはずなのに、
何故人々はわざわざ自ら恐怖を味わいたいと思うのでしょうか?
それにはいくつかの理由が考えられます
脳内ホルモン
アドレナリンが脳内で放出されることで、脳は覚醒しスッキリします。
また危機を脱したときにはドーパミンが放出され快感を感じます。
こうした刺激が快感となっていることが考えられます。
安心感
ホラー作品は実際の危機に直面せず、安全な環境で統制された恐怖を味わうことができます。
これによってより安心感を感じることがえきます。
開放感
安心できる環境でネガティブな感情を味わうことは、日ごろのストレスの解消につながります。
こうした感情の開放は、ストレスや不安の軽減につながります。
達成感
たとえ疑似体験であったとしても、恐怖を乗り越えることで私たちは達成感を味わうことができます。こうした達成感は自己肯定感にもつながります。
ホラーコンテンツは一大市場として注目されています。
それだけ私たちは安全な恐怖体験を潜在的に求めているのかもしれませんね。
学習の合間に、ホラーで息抜きしてみるのはいかがでしょうか?
スッキリして、また学習に集中できるかもしれません。
参考
関講師が担当するNLP(実践心理学)が気になる方は、是非チェックください。
受講生・修了生向けセミナー・イベントページ『学びコネクト』にも
心理学関連イベントが掲載されています。是非ご興味に合うものを探してみてくださいね。
関 一真
-
心理
担当
京都四条烏丸校
所属
NLP™トレーナー、心理カウンセラー2015年より京都校、大阪梅田校にて心理学系講座を担当。優秀講師賞受賞。個人で心理カウンセラー、占い師としてクライエント様に相談援助を行う。日本語教師(日本語教育能力検定試験合格)、社会福祉士資格保有
この講師の記事を見る